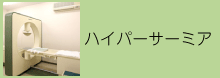全体朝礼より
更新日:2021/01/08 18:20 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「年頭挨拶」でした。
俊野常務の講話「「ぶる」のではなく「らしく」を目指そう 」から
皆さん、明けましておめでとうございます。また年末年始にも勤務に当たってくださった皆さんお疲れ様でした。
さて今年2021年は丑年ですが、結和会が発足した平成21年も丑年でした。ちょうど一回りしたことになります。
丑年といえば、子年に蒔いた種が芽を出して成長する時であるとか、また牛歩(ゆっくり歩んでいく)などが思いつくのではないかと思います。
我が家では、毎年正月の朝に私が考えるその年のテーマを伝えることが恒例となっています。今年はコロナのことがあって家に集まることが出来なかったのでラインで伝えることになってしまいましたが、『「ぶる」のではなく「らしく」あれ』をテーマにしました。
「ぶる」はふりをするということですから本当の中身が伴っている状態ではありません。
一方「らしい」は根拠や理由のある推量をさす助動詞ですが、名詞が前につくと、○○らしくとなります。例えば医療人らしくとか父親らしくなど、○○に相応しい、中身が伴った状態を意味します。ふりをするのではなく本物を目指したいと思いこのテーマに決めました。
皆さんもコロナ禍の中で、業務だけでなく私生活においてもストレスが多いこと思いますが、自分のなるべき姿を目指していただければと思います。今年も笑顔で頑張りましょう。
更新日:2020/12/08 15:11 カテゴリー:朝礼
俊野常務の講話「百聞は一見に如かず」から
皆さんおはようございます。急に寒くなって、朝気持ちよく布団から出られなくなってきました。
先ほど院長よりコロナ禍の中での生活のあり方についてお話がありましたが、皆さん「今年の賞与はどうなるんだろう」と気になっているのではないかと思います。正直言ってコロナ禍により患者さんが減少しているので、前年の10%減で予算を組んでいましたが、9月末の決算では前半戦の頑張りが利いて何とか前年をキープできました。したがって賞与も見直しをしています。管理職の皆さんは若干マイナスとなるかもしれませんが一般職員の皆さんはほぼ前年並みの見込みです。大きく減額とはなりませんので賞与での支払い計画がある方も心配しないで大丈夫です。
それはさておき、今、自宅を建築中なのですが、外壁の色から始まって壁紙や照明など様々なことを決めなければならず大変でしたが、やっとある程度落ち着きました。外構については車庫と農機を置く場所を取り、残った空間に植木を植えてシンプルな塀をつくる程度でいいと思っていたので、私のイメージを簡単な平面図にして家内に説明しました。ところが日本語の分からない外国人に話しているのかというくらいイメージが伝わりませんでした。
しかし、このところコロナ禍で出掛けることもないので、ウォーキングを一緒にするようになり、道々色々な家の外構を一緒に見るようになりました。それでやっとイメージを共有できるようになりました。「百聞は一見に如かず」と言いますがまさにその通りだと思います。
子どもは親の背中を見て育つといいます。また研修等でも文字だけでなく映像を見た方がわかりやすいですし、更にロールプレイングで実際にやってみると更に理解しやすいと思います。「わかったつもり」ではなく「わかる」「正確に共有する」ことが出来るよう工夫をしていきましょう。
更新日:2020/11/17 17:06 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「冬場の感染対策について」でした。
俊野常務の講話「記憶」から
朝晩寒くなり、朝目覚めても布団が恋しい季節になりました。ところで「親の足を洗うⅡ」を先月の給与に同封しました。その中で母がどう思っていたのか聞けなかったと書きましたが、今回長期入院になるため改めて荷物を整理していたら、古い日記が出てきたので、何か感想が書かれていないかとページをめくってみました
足を洗わせてもらったのはH24年のことですが、一年前のH23年7月以降は何も記されておらずH21年6月27日の日記に「物忘れがひどく頭がボーとする」と記されたのを皮切りにその後も頻繁にそういった内容が書き込まれていました。ある日のページには「頭がボーとしているのも、誰かがしてくれると甘えの気持ちがあるからだろう F子!しっかりせよ。マダマダボケルの早いぞ!」などと記されていました。
買い物に出かけてはバナナを買ってきて「お父さんが好きやからバナナを買ってきたけど、買い過ぎたからお食べ」とバナナをくれていた母に、「またバナナ?最近ボケてきたんと違う?」なんて返していましたが、そんな思いを抱えていたとはまったく気づいていませんでした。
現在認知症が進み寝たきりになっている母は、自分で排泄物を片付けることはもちろん、足を洗うことも顔を洗うことさえできません。そんな母にとって足を洗ってもらったり、入浴をさせてもらうことは明らかに「快」だと思います。言葉には表せなくても「快」なのか「不快」なのかは感じていると思います。お礼やご意見を言って下さる患者さんも、何も言わずにベッドに横たわっている患者さんも同様に心のこもった看護・介護をお願いしたいと思います。
更新日:2020/10/06 14:49 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「節目」でした。
俊野常務の講話「無意識に注意」から
皆さん、おはようございます。
先ほど院長からお話がありましたように。この9月の決算は新型コロナの影響を受けましたが、前半戦の頑張りにより予算比は、若干のマイナスですみそうです。経費はコロナ対策により増加しましたので利益は減少となりましたが、経営が厳しいというレベルではありませんのでご安心ください。ただし、このまま患者数の減少が続くと大変なことになってきますので、いつでも新規の患者さんを受け入れられるよう準備を怠らないようにしましょう。
それはさておき、皆さんは無意識のうちに○○なことをしてしまっていた、という経験はありませんか。
わたしは、先週の日曜日にちょっと気になったことがあって出勤しました。ちょっとだけだからとジャージにサンダル履きで来ていました。
小1時間ほど仕事をして帰宅したのですが、家の玄関でなんとなく違和感をおぼえていました。しばらくして家内が「パパ、サンダルが違うよ」というので見にいったら、ふだん院内で履いているサンダルが玄関に脱いであったんです。違和感の原因はそれでした。
普段、出勤して朝礼が終わったらサンダルに履き替えているのですが、その日はサンダルで行ったのに、わざわざ違うサンダルに履き替えて、そのまま帰ってたんです。
履き替えたという記憶は全くありません。無意識のうちに履き替えていたんだと思います。
サンダルくらいは「ついうっかり」で、笑い話で済ませられますが、ルーティンワークで習慣になっていることもたまにはチェックが必要だと思いました。
「ついうっかり」からインシデントやアクシデントに繋がらないよう注意しましょう。
更新日:2020/09/08 15:09 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「感染対策の継続」でした。
俊野常務の講話「常識の共有」から
指示されるときと指示するとき、それぞれ気をつけないといけないなと思ったことがあります。
その場で常識(知識)が共有されているかどうかという事です。たとえば、皆さんは漠然と燃料といわれたら何をイメージしますか?車のガソリンでしょうか、それともストーブの灯油でしょうか。農業機械では、トラクターやコンバインは軽油、田植え機はガソリン、乾燥機は灯油となっていてこれは私の中では常識です。もし私がコンバインに燃料を入れておいてとお願いしたら、わからない人はガソリンを入れてしまうかもしれません。
また逆の立場でいうと、家内が魚の煮つけをつくっている途中で来客があり、ちょっと見といて…と声をかけて台所を離れたので様子を見ていたのですが、なかなか帰ってこないので火を止めておきました。戻ってきたので「焦げたらいかんから火を止めたよ」と伝えると、「落し蓋をしといてくれたらよかったのに…」と、料理をする人からしたらそれが常識かもしれませんが、よくわかっていない人には細かく指示をしないと自分の思っているようには動いてくれません。そこは理解しておく必要があります。
気が利かないのと知らないのでは大きな違いがあります。知らない人は知ったら出来るようになる可能性がありますので、指示内容が共有されているかどうか確認する習慣をつけましょう。匙加減という言葉も、ある程度わかっている人同士で通用する言葉だと思います。
また、間違いやミスを見つけたときは爽やかにその場で教えてあげましょう。後になると言いづらくなってしまう場合があります。咎めるのではなく、その場で注意を促すことも大切だと思います。知識は共有されて初めて常識となるのだということを頭に入れて笑顔のあふれる職場をつくりましょう。
更新日:2020/08/18 10:03 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「職員の安全確保について」でした。
俊野常務の講話「継続することの難しさ」から
皆さんおはようございます。この数ヶ月色々な制限がありますが「ウィズコロナの生活を確立させましょう」とお話をしてきましたが、私自身これをしようと決意したことが中々継続できていません。
一つはジムを休会したために、「腹回りが緩んできたので腹回りを絞る」と決め、腹筋運動を始めましたが、一日二日実行すると腹筋が痛くなり、無理をしないで今日は休もうと理由をつけて休むとしばらく忘れてしまっていたりします。
また本を読むという事に関しても、皆さんに本をご紹介した時に5冊まとめ買いしましたが恥ずかしながら未だに読み切っていません。これは、アマゾンプライムに加えてネットフリックスを契約してしまったため、ついそっちの方に時間をとられてしまっているからです。
しかし、そんな私でも毎朝仏壇にお茶と水を供えてお参りをしていますし、お墓の掃除にも通っています。
ご先祖様に申し訳ないとか、さぼって家族に何かあったらいけないと思うと継続することが出来ますが、すぐに結果が出ないことや自分だけのことだからと思うとつい甘えが出てしまいます。
皆さんも毎朝の体温測定やマスクをつけることは、習慣化され特に意識をしなくても続けられるようになったと思います。今後一層の自粛生活や感染防止対策を継続するには家族や同僚と意識の共有が必要になってくると思います。
私自身においても、家内や娘が「今日も腹筋をしたの?」と認めていてくれたらもう少し継続できるのではないかと思います。
一歩踏み出すことより続けることの方が難しいこともありますが、共有しあって頑張りましょう。
更新日:2020/07/08 9:40 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「感染対策の継続について」でした。
俊野常務の講話「ウィズコロナの日常」から
皆さんおはようございます。
梅雨と夏の気温上昇でコロナウイルスが少しはおとなしくなるかと期待をしていましたが、首都圏ではまた盛り返してきて嫌な感じになっていますね。
ウィズコロナの生活ということで、ビデオを見たり読書をするのもいいですよと、本を紹介したりしましたが、私自身のんびり過ごすことに慣れてしまったのか、時間はたくさんあるはずなのに以前より本を読むペースが遅くなっています。色々やることが多い時には、この時間にここまでは読もうと目標を決めて集中して読んでいましたが、最近では少し読んだらいつの間にか寝落ちしていたりして中々読み終わりません。ナマケぐせがついてしまったのかなと思う反面、時間があるのだからこれでいいのかもと考えてストレスにしないようにしています。
職場においては否が応でもコロナウイルス感染対策に神経を使い、ストレスがたまりがちです。せめてオフの時にはゆっくりとストレスを溜めないように過ごしましょう。
そしてこれから本格的に暑くなってきますが、熱中症に気を付けて体力を維持し抵抗力を落とさないようにしましょう。
また間もなく夏の賞与が出ます。院長からお話があったように今回は年初からの頑張りにより10周年の昨年よりは減少しますが、例年並みに支給することになりました。しかし今後の患者数の増減いかんでは冬の賞与には影響が出てくる可能性があります。患者さんが安心して来院・入院できる体制を維持して頑張っていきましょう。
更新日:2020/06/06 9:13 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「北九州の事例から学ぶこと」でした。
俊野常務の講話「新型コロナから学ぶ」から
皆さんおはようございます。
自粛生活が効いてきたのか新型コロナウィルスも少し大人しくなってきましたが、まだまだ油断はできない状況が続いています。
先日、「感染列島」という映画を観ました。2009年に制作された妻夫木聡主演の映画で、日本が未知のウィルスに侵されなんと4000万人が感染し1100万人が死亡するという恐ろしい内容です。数年前に一度観たことがあるのですが、その時は普通にストーリーを追って興味本位に観ていました。しかし今回はついつい医療現場でのシーンが気になってしまい、防護服の着脱の仕方や医師や看護師さんの心理状態などに目が行ってしまい、前回とは明らかに見方が異なっていました。今回の新型コロナウィルスの感染防止対策が意識されているからだと思います。
幸い今のところ当院では感染者が出ていません。皆さん一人一人が他人事とは考えず、我が事ととらえて感染防止対策をとり、私生活においても自粛をしてくれているおかげだと思います。そしてこのことは私たちの感染対策のレベルを大きくアップさせてくれていると思います。
四国地方も梅雨入りしたようです、気温や湿度の上昇によりウィルスの活動が抑えられることを期待していますが、引き続き引き締めていきましょう。
また院長からお話もありましたように4月、5月の売上減少分もカバーすべく新型コロナ対策をとりながらも積極的に患者さんの受け入れもしていかなくてはなりません。ただ年度前半の皆さんの頑張りのおかげで、これからの踏ん張り次第で十分カバーが可能ですのでよろしくお願いします。
更新日:2020/05/01 18:46 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「院内感染の防止対策について」でした。
俊野常務の講話「生活の断捨離」から
皆さん、おはようございます。
全体朝礼で毎月こうしてお話をしていますが、院長と打ち合わせをしているわけではありません。それでもほとんど内容が被ることはありません。さすがにこのコロナ禍の中では被ってしまいました。
緊急事態宣言の延長が近日中に発表になりそうな様子ですが、院長がお話ししたように感染防止対策と共に長期間にわたる行動の自粛が必要となります。
短期間なら徹底した自粛により3密を避け、手洗いやマスクの着用などの予防策を併用してやっていくことも可能ですが、長期間の我慢となるとストレスがたまります。またどうしても必要なことや、やりたいことも出てきますので、改めて生活の断捨離をして新しい自分のライフスタイルを確立していく必要があります。たとえば私としてはゴルフの練習は可と思っていますが、家内の基準では否です。折り合いをつけたところで新しい生活のパターンを作っていこうと思います。
このまま収束に向かってくれればいいのですが、長い戦いになっても大丈夫なようにしっかり対応していきましょう。
更新日:2020/04/09 13:26 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「新年度を迎えて」でした。
俊野常務の講話「コントロール出来ることはコントロールする」から
皆さん、おはようございます。
さて皆さんも毎日新型コロナウィルス感染拡大のニュースばかりでうんざりしているのではないでしょうか。松山は大丈夫なのか気になるところです。
そんな中で新年度を迎え、新体制でのスタートとなります。マスクをはじめとした医療用品の不足もあり不安なことも多々あろうかと思いますが、こんな時こそ情報を共有し、院長中心に全員一致団結して、一人一人が「コントロール出来ることは確実にコントロールする」をスローガンにこの危機を乗り越えましょう。
今、私たちが置かれている状況はまさに実戦そのものです。研修と違ってやり直しができるわけではありません。緊張感をもって本気で取り組めば取り組むほど自らのレベルを引き上げてくれるのではないかと思います。もちろん笑顔は忘れないでお願いします。
また新しく入職してくださった皆さん、そして本日昇進した皆さん。それぞれの役割を自覚しどんな時も笑顔で前向きに頑張ってください。よろしくお願いします。